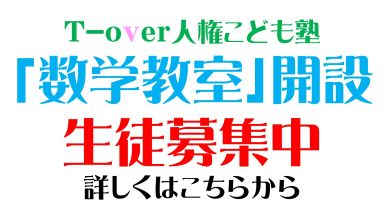八万中学校3年生第2回学年全体人権学習
「3年生人権作文意見発表会」
7月5日(金)、午後の時間を使って、3年生による人権作文意見発表会が行われました。
暑い暑い体育館アリーナです。窓はすべて全開。巨大扇風機が何台も周りを囲むなか、各クラスの代表6人が、人権委員会進行のもと、意見発表をしていきます。
まずは前半3本。
3組「人権学習のカタチ」
4組「個性とコンプレックス」
2組「引っ越しがあったから、今の自分がある」
どれもが違った新鮮な視点でした。これまでの人権学習のカタチを変えてきた経緯とその思いについて。自分のコンプレックスが他の人には長所にもなり得るということについて。そして、小学校から何度も繰り返してきた引っ越しから自分が学んだことについて。
前半を終えて、全体で意見交換を行いました。
①「今の人権学習の形は、人権委員のみんなのおかげだと思うので、感謝したいです。」
②「自分もそのときは人権委員で、みんな同じ悩みを持っていました。たくさん話し合い考えたことを実行したことで、みんなの心を動かせられたと感じました。」
③「Yさんの発表を聞いて、人権学習の新しいやり方で発表者が増えていったことだったり、その達成感があったりで、共感できることがいっぱいあったのと、人権学習を身近なものにするということの大切さが伝わってきて、自分もこういう考えで人権学習に取り組みたいと思うようになりました。」
④「Yさんの話を聞いて、確かに人権学習を特別なものにしてしまえば、これから先、きっと私は人権学習を続けていかなくなるかもしれないと思いました。だから日常の一部にしていきたいと思いました。」
⑤「Tさんの発表を聞いて、自分もコンプレックスがあるけど、そのコンプレックスもとても魅力的なものだと気づかされました。自分の嫌なところもいいことだと考えて、そのコンプレックスの良さに気づいていきたいです。」
⑥「Tさんの質問を聞いて、自分が短所だと思っていることでも、人によっては長所になり得ることが分かりました。人権学習で「恥じることでないことを恥じるとき、本当の恥になる」という言葉を学び、自分でも一度見直してみようと思いました。」
⑦「Oさんの、友達ができて別れての繰り返しや、引っ越しのサイクルがつらかっただろうけど、その別れによってたくさん学ぶことがあったりするんだなと思いました。あと、ディズニーランドの「笑うことは人を幸せにする」という言葉を聞いて、すごいなと思いました。」
やはり、人それぞれ、ヒットする内容は違うんですね。共感したと伝えたり、友の気持ちの変容が自分の自信につながったり、そこからまた新たな学びが広がったり。。。教師の千の言葉より、同級生の言葉は染み込んでいくのだと、つくづく思わせられます。
つづいて、後半3本です。
6組「男女差別について」
1組「なりたい自分」
5組「人権に「普通」はいらない」
「虎に翼」に見る、日本の女性差別の変遷について。自分も女子であることで不自由を感じてきた。今までの学びが今の自分をつくっているので、この3年間の人権学習をこれからにつなげていきたい。背が高いというコンプレックスについて、短所を長所に変え、人生を楽しんでいきたい。克服した母は自信があってカッコイイ。マイナスをプラスに、自分がされて嫌なことは他人にしない。性別にルールはいらない。体の性と心の性は違う。日常にある差別的な会話。人権に「普通」ということばはいらないのではないか。
後半を終えての全体の意見交換。
⑧「さっき発表してみて、最初Tさんの発表を聞いたときに、自分も全く同じ内容書いてると思って。同じ意見になるのか不安だったんですけど、やっぱり人が違うと見方が変わるので、同じ題材でもまったく違う内容だなと安心したし、やっぱ人って違うんだなと思いました。」
⑨「Mさんの発表を聞いて、罵声を浴びても力強く生きることが大切って聞いて、それは現代であってもSNSで互いの顔は見えないけど、有名人に暴言を吐く人がたくさんいて、自殺して、そんな苦しんでいる人にこの作文を読んでほしいと思いました。」
⑩「TさんとMさんの発表を聞いて、私も少し背が高めで、無意識のうちに姿勢を悪くして、少し背を低く見せようとしてた時期がありました。自分がコンプレックスだと思っていることも、誰かにとってはうらやましいと思ってくれることもあるだろうし、自分の気持ちの持ちようで、自分がコンプレックスと思うのか、長所だと思うのかが変わるのだと思いました。」
⑪「Kさんの発表を聞いて、私たちは今自由に生きる権利があります。それは昔は無理だったことです。だから今私は好きなように、自由に生きていこうと思いました。」
⑫「Mさんの発表を聞いて、短所も長所も長所にして、長所だらけにするという言葉に惹かれました。わたしも長所より短所が多いから、この言葉に助けられました。なりたい自分になるには、自分の好きじゃない部分も好きにならなければならない。私も自分を愛せるようにしていきたいです。」
⑬「MさんとTさんの意見を聞いて、二人とも自分のコンプレックスに向き合っていて、メチャカッコイイと思いました。人それぞれ悩みとかコンプレックスがあって、何も考えずに言葉を発すると傷つけてしまったり、逆に救えてしまったりして、人の行動は自分にとって、自分の行動は人にとってとても影響があるんだなと思い直しました。あとDさんの意見を聞いて、少し安心しました。自分も同じ意見だったので。性別はグラデーションていう気が自分はしてて。何万通りもあって。誰一人として同じ人はいないかなと思ったので、同じ意見の人がいて安心しました。」
⑭Kさんの発表を聞いて、わたしもそのドラマを見ていて。Kさんがもっとその人のことを知ってほしいと言ってて、私もドラマを見たときに、なんでこんなに苦労をしてるのに、見た目だけとかで、その人を知らないだけで、こんなにひどいことができるんだろうとすごく思ったし。それは昔のドラマだけど、今でもそういうことを自分がしないように、そして人がそういうことを他の人にさせないように、自分は人と対話をして人の思いを知ることをもっと大事にしていきたいなと思いました。」
⑮「Kさんの発表を聞いて、私も実はスカートはくのとかちょっと苦手で。同じ人がいてちょっと安心しました。ドラマの話を聞いて、昔あった差別を昔のことだからといってなかったことにするんじゃなくて、私は昔闘った人たちの気持ちも背負って、こういうことがあったんだよって後の世代にも伝えて、そういう差別がなくなっていくようにできたらいいなと思いました。」
⑯「MさんとTさんの発表を聞いて、友達との接し方を考えました。見た目ばかりじゃなくて内面を見てあげるようにして、特に短所ばかりじゃなくて、長所もたくさん見てあげようと思いました。他にも、知らないうちに友達を傷つけてしまうから、礼儀をもつということも大切にしようと思いました。友達は血もつながってなくて、近くに住んでるわけでもなくて、でも助けあえて支え合える唯一の存在なので、生涯大事にして一生人生ともにできるように、これからも大切にしていこうと思いました。」
⑰「Mさんの発表を聞いて、コンプレックスを克服できた祖母の助言を自分に言い聞かせることができたからこそ、自分に自信がもてたことに感心しました。前向きな性格をもち、ポジティブに捉えることこそが、心への負担が軽くなれるのだなと思いました。」
⑱「Dさんの発表から、性別は関係ないのだということを思わされました。一人ひとりの感性を大切にし、これからの社会を構築していこうと思いました。」
⑲「様々な個性を持っている人がいて、そのなかでも世の中でまだ認められていない人がいるのが現状です。しかし世の中は少しずついい流れになりつつあります。その流れを正すのがZ世代であろう僕たちの役目です。」
不思議です。暑かったはずなのに、思うほど暑く感じませんでした。フロアの中学生を見ていてもそう感じました。それだけ集中できていたのかもしれません。
意見発表の一つ一つにしたいコメントがあり、その後の意見交換で出てきた発表にもしたいコメントがあります。このあと感想文が届いてきますが、そこにもコメントしたいことが出てくるのでしょう。いろんな思いが膨らみます。
私からも、「八中方式」を編み出し実践してきた自分たちに自信と誇りをもって、このステップを次の行動に結びつけてほしい。旧優生保護法や徳島大空襲、沖縄で起きている米兵による女性暴行事件を引き合いに出しながら、遠くのことを近くのことに、近くのことを自分事にできる自分に変わっていきましょうと、話させてもらいました。もちろん、中学生集会や新聞切り抜きコンクールについてもアピールし、最後に、自分たちの、私たちの未来を変えていきましょうと、語りかけて会を終了しました。
さて、それでは、人権だよりの作成にとりかかります。私、やっぱり、この学年の子たちが、好きだなぁと思います。